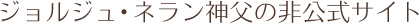『遠藤周作に付いて G・ネラン』
遠藤氏の作品の唯一の主題は、人間の弱きである。もちろん色々な形をおびているが、このテーマは、単にすべての作品を貫いているだけではなく、常にその芯になっているのである。烈しい感情に富んだ『海と毒薬』のような作品では一読しただけでは、この人間の弱さが明瞭には意識されない力もしれないが、疑いもなく潜んでいるし、しかも中核をなしているのである。もし遠藤氏が、一つの犯罪の心理的解釈を施したかつたのならば、主人公として主任教授を選ぶべきである。しかし主人公は勝呂である。勝呂は、犯人のうちでは、事件に最も関係が薄い。勝昌がその事件で端役をしか演じなかつたのは、彼が弱いからである。遠藤氏は、勝呂の、その弱さをクローズアッフしたかったのに違いない。
勝呂の弱さを強調するために、戸田の強さが描かれている。数回にわたって、「お前は強いなあ」と、戸田にむかつて言っている。戸田が勝呂と対照的な人物として登場する理由はそこにあるわけであるが、ともかく彼の非情な強さは、いささか不自然に見える。それを意識してか、作者は、戸田の強さを説明するために、彼の成長の道を迪ってみせるのである。だから読者は、戸田の態度が理解できるのである。逆に我々は、勝呂の少年時代については、何も知らされない。人間の弱さには、説明が要らないからである。
「出来なかつた」という言葉は、弱い勝昌をよく表わしている。彼は、「おばはん」の件で、患者を苦しめることが出来なかったし、予備検査を命ぜられた時にも、断わることが出来なかつた。更に、生体解割に参加することが出来なかったし、手術室でエーテルを嗅がせることも出来なかつたし、その部屋を出ることも出来なかつた。そして最後に一それは作品の最後の言葉であるが一一一流行歌を歌うことも出来なかった。
また、「お前、甘いねえ。いつまでそんな女子学生みたいなこと考えてるのや」と戸田に言われて、顔を赤くする。勝呂は徹底的に弱い人なのである。しかし、弱いからこそ我々の共感を起こすのである。彼には人間味があるが、その人間味は、まさに、弱きに由来するのである。弱い好人物を描くことは、遠藤氏の作意であったろうし、また、弱いから愛されるということも、遠藤氏のいわんとしたことではなかったろうか。
戸田は自己弁護し、「あなた達も同じだ」と唱えて、人間の共通性に訴えようとするのであるが、勝昌の無言の弱さの方が、はるかに強く、我々の心を動かす。十何年かたって、勝呂は腕のいい、また、勘定をあまりやかましくいわない医者になった。いわゆる善人なのである。しかしやはり「これからだつて自信がない。これからも同じような境遇におかれたら、僕はやはり、アレをやつてしまうかもしれない」と言う。彼は、今はある種の強さがあるのだが、なお弱さが残っている。彼の強さが、その弱さから来たものである、という仄めかしがあるのではなかろうか。
勝呂が主犯ではないと同様に、『白い人』の主人公である「私」も、主な拷間者ではない。キャバンヌとアレクサンドルが拷問するのであり、「私」は単なる通訳として付き添っているにすぎない。そして、相手を苦しめようと思うと、「私」は肉体を鞭で打つのではなく、精神的な武器をもって攻める。こういうふうに、遠藤氏は、残酷なことを語っても、そのサディズムを分析するのではなく、ジャックと「私」との対決を物語るのである。拷間の物語ではなく、傲慢の決闘なのである。
言うまでもなく、「;私」は嫌な人物である。また、「私」は斜視である。斜視であるから、そして、ああいう母、ああいう父の子であるから、ああいう環境に置かれたから、「私」は悪人になった。その経過は必然的だとは言わないまでも、少なくとも自然である。そこに遠藤氏の主眼がある。つまり、我々は誰でも、「私」の境遇に置かれたら、「私」同様、悪人になる。だから、「私」に悪を感じるよりは、人間の共通の弱さを悟り、そういう「私」になんら反感を抱かないのである。不思誠に、善人であるジヤツクは好感を起さず、悪人である「私」は反感をいわないのである。それには、この小磯の語り手が「私」であるという理由もあろうが、その印象は、作者の意図したところではなかったであろうか。すなわち我々は、見かけによって人を是非するのではなく、悪人をも理解すべきだというのである。
「私は斜視であり、ジヤツクは醜い。2人とも同じ条件のもとにおかれている。そして勝負があった。しかし、誰が勝ったかは、よくわからない。1人は英雄主義に酔って、1人は悪に酔って、どちらも自分の醜さという弱点を乗り越えようとする。勝負そのものよりは、その2人の闘いと、それによって互いに似かよってくることとに作者は重点を置いたに違いない。2人とも弱い者である。そして2人とも、その弱さの活路を懸命に探している。けれども、活路はありそうにない。
『白い人』は、遠藤氏の出世作である。こういう初期の作品にも、素朴な形で、ではあるが、あの主題は、既に明瞭にあらわれている。人間は弱く、その弱さから脱出する道を求めている。ジャックの英雄主義は、あまり魅力がない。むしろ、読者は、弱い「私」に対して、犯罪人に対する憎しみよりも、不幸な人間に対する同情を覚えるのである。罪人は、慈悲を乞うみじめな人間なのである。それこそ遠藤氏の語ろうとするところではあるまいか。
人間はみな弱い、また人間はみな罪人である。これは、キリスト教の一つの原理であるに違いない。そして、弱い者に対する同情や罪人に対する寛大な心は、キリストの態度であり、その弟子の理想でもある。弱い者に対する人情を呼び起す作品なら、それだけでもキリスト教的な作品と呼ばれる資格がある。しかし遠藤氏の作品の中には、弱さについての、もっと深い見方がある。「神は、知者をはずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い事をはずかしめるために、この世の弱い者を遊び----」(コリント前書1-27)と聖:書にある。神が弱さを強さに変えるというのは不思議な教えであるが、確かにキリスト教の一つの奥義である。信ずるのは、この世が絶対者たる神によって支配されることを認めることである。とすれば、神の絶対性とこの世の相対性との衝突が我々を迷わせるのは当然になるであろう。つまり、神の業における不思義な面は、神の超越性を表すのである。この神学説はともかく、聖書の言葉は、よく考えれば、理解できないことはないであろう。
もちろん、人に|ま弱点があるから、その外にどこかに強点もあるはずだという意味なら、あまりにも単純な、皮相な考え方である。聖書の教えるのは、そうではなく、弱さそれ自体が強さに変えられるということなのである。人間が弱い者であることを徹底的に理解すれば、自分のすべてを神に任せることになり、そして神の御旨に抵抗しない弱さを通して、御方が顕われる、と説明すればよかろう。あるいは、自分の弱さを認める謙虚さこそ、真の強さの土台になると言っていいかもしれない。ともかく、弱さと強さとは別々のものではなく、弱さそのものが強さになるのだということを、聖書は説いているのである。弱さを強さに変える錬金術師が神である。これが、遠藤氏の小説を解き明かす鍵となるのである。
そういった主題は、『札の辻』という短編ではなまのまま出て来る。主人公のネズミの弱さが、余すところなく強調される。貧弱な体、不器用な男、臆病な男、死ぬのをこわがっている子供のように泣き叫び、セックスは豆のように小さい、殴られる人を助けようとせず、逃げ出すことさえできない、といった表現をひろっただけで、すぐに納得がいくであろう。ところが、そのネズミは、後に身代わりとなって英雄の死を遂げたという報せが来る。それが確認されるわけではないが、作者はそれを、確かな報せとして受け取っている。ネズミという臆病者が殉教者に変えられた。この錬金術は誰かを問題にするために、作者は「だれがネズミにそんな変わり方をさせたのだろう」と、念の入ったオチをつける。
ところで『札の辻」では、ネズミの物語が、「男」の現代生活の描写の中にはめこまれている。いわば、二重写しなのである。男の弱さはネズミの反映である。そうだとすれば、ネズミの強さに照応する男の強さもあっていいはずだが、その方は述べられていない。しかし、臆病者すら英雄に変えられるという教訓は、まして普通人たる我々には当然それが出来る、ということを、それとなく示しているのではなかろうか。
二重写しの手法は『その前日』にも、大いに使用されている。病室に寝て、大手術に直面する「私」と、踏み絵の試練に直画する村人達が並列されている。背景では、臆病者のキリシタンである藤五郎は転び、しかも回心してからも再び転ぶ。前景では、病人の「私」は幾度かの失敗に襲われている。不吉な前兆として、嫌な男がエロ写真を売りに来たり、見たかった踏み絵が見えなかったり、手術の準備が冷たいメカニックのように進んだり、こけし人形さえ転んだりするのは、ちょうど、迫害が藤五郎を取り囲むように、「私」を容赦なく厚い壁で取り囲む。「私」は、弱さそのものになった。そして「私」は、藤五郎のように、その前日のあくる日に―死の中に一転ぶであろう。
転ぶ。しかし転ぶのは、キリストの愛を拒否することではない。キリストが、人間の中の最も弱い人であるユダを愛したからである。キリストは、人間の弱さを理解し、分かちあい、背負うのである。そして、遠藤氏によれば、キリストの愛は、人間の弱さに優って、藤五郎の臆病をも、「私」の恐怖をも、包んでしまうのである。
『40歳の男』は、遠藤氏得意の病人物語の1つである。病人のみじめさ、弱さの描写にま、他の作品にも勝る豊かな才能の閃きがある。ここでは、病人としての弱さに罪人としての弱さが咄み合っている。能勢と称する主人公は、内体的にも精神的にも弱いのである。ところで、その弱い能勢を取り囲む人々は、みな親切で、彼を慰めたり、励ましたりする。妻も微笑で赦し、司祭も赦そうと思う。医者も看護婦も、優しい言葉をかける。しかし,その温かい言葉は、鋭い言葉よりはるかに残酷に聞こえる。対照的に病人のみじめさを一層引き立てるからである。他人の激励はむなしい。むしろ彼を弱さのどん底まで突き落とすだけである。能勢の助けとなるものは九官鳥だけである。その九官鳥は彼の代わりに死んだ。人間を弱きから救うのは、身代わりになって死んだものの外はないと、作者は心で叫んでいたのではなかろうか。
『おバカさん』という題は、それ自体、主人公の性格を十分に語っている。ガストンの愚かさは容赦なく描かれる。馬のような顔、みすぼらしい服装、礼儀を知らない、間のぬけた男、不器用、非常識、女にもてぬ、弱虫、臆病者などという表現が随所に現われる。巴絵の言う通り、すべての点で、ゼロ。ゼロ・ゼロなのである。
作品の終わりで、作者は、ガストンの秘密を解き明かす。「布教神学校に3度も落第した所のわるいぼくだが、やはり日本に行きたい気持ちに変りがない」と。ガストンが善良な人であり、熱心なキリスト教徒であることが、判然と読み取れる。ガストンの愚かさと善良さという2つの極の間に、作者は小説を編んだのである。
もし遠藤氏が、ガストンの愚かさと善良さを並べて、単に1人の人物の2面を描こうとしたのならば、この作品の評価も、おのずからそういった限界を有することとなろう。ところが、遠藤氏の意図は、もっと深いところにある。すわち、ガストンは、愚かであるにもかかわらず善良なのではなく、愚かであるが故に善良なのである。善良さが、愚かさそのものから生まれる、それが氏の作意なのである。換言すれば、愚かさの底にあるものこそ善良さなのでる。それを表現するために、作者は、ガストンの成功と失敗を並べることなく、ガストンの同一の行動に、二重の意味担わせたのである。
例えば、ふんどしの件の場合、ふんどしはガストンの愚鈍を示すと同時に、殺し屋遠藤の助けになる。また、ガストンは臆病だから相手のなすがままに殴られているのだが、その弱い態度こそ、形式上の負けよりも、好感を呼ぶ。ガストンは、遠藤殺し屋に対して恐怖を抱いており、「こわい、こわい」と告白している。そしてこわいから、殺し屋に何ら抵抗を示すことが出来ない。が、その無気力で無能な態度は殺し屋の敵意をむなしくする。結局、ガストンは弱さのおかげで助かる。女にもてぬ、男を愚弄しようと思つっ巴絵が「ガストンさんには恋人がいらしゃるのと尋ねると、彼は頑是ない返事をして、巴絵さんの事、好き」と答える。
この天真爛漫さが、彼女の心を動かさずにはおかない。また、ガストンは野良犬が好きである。彼自身が野良犬だからである。ガストンは子供が好きである。彼自身が子供だからである。その幼稚さは、彼の尽きざる愛想となって顔を出す。間のぬけたガストンと愛くるしいガストンとは、同じ場面の同じ動作で、唯一のガストンの姿を成している。
ガストンは失敗を重ねてばかりいる。入学試験でも、隆盛の家でも、旅館でも、「彼がすること、なすこと、いつも同じあわれな、ぶざまな結未になるのである」。しかもそれを十分に意識している。「こわい、こわい」「はい、ハイ」と言う彼である。しかしそのことは、結果としては、失敗どころか、彼のお影で、巴絵は、もっと深い人生観を発見するし(「あたしは今日まで男性というものをあまりばかにしていたのかしら」)、金井と小林という2人の男が命びろいをするし、殺し屋さえも僅かながら友情を単えるに至るのである。それは、まさに、弱さの勝利である。こ隆盛の言通りである。「人間はみんなが、美しくて強い存在だとは限らないよ。生れつき臆病な人もいる。弱い性格の者もいる。メソメソした心の持主もいる。けれどもね、そんな弱い、臆病な男が自分の弱きを背負いながら、一生懸命美しく生きようとするのは立派だよ」と。隆盛なりにそう説明するのが、読者にはさらにこうつけ加えたいだろう。
ガストンは馬鹿にされている。しかしその軽蔑はやがて好感に化していく。その錬金術を行なうのは、ガストンの純粋な愛である。彼は自分の利益のためには何もしない。人の世話をしたり、人のために努力を惜しまない。自分が何を食べるか、どこに泊まるかなどは、一切お構いなしである。友達になった遠藤のために危うく命を落としそうになる。もっともガストンは何も持っていない。才能も職業も地位も。目的さえもない。あるとしても、それは日本を愛する事しかない。ガストンは貧乏人そのものなのである。しかし「何も持たないようであるが、すべての物を持っている」という聖書の言葉を、身をもって示している。あるいは、「あなたがたが彼の貧しさによって富む者になった」という聖句の「彼」はキリストを指すが、信者であるガストンもその「彼」にふさわしいかもしれない。
神の力によって弱さが強さに、愚かさが知恵に変えられるが、それには、条件として、人間の謙遜を要する。人はまず、自分の弱さを認めなければならない。その点について、『白い人』のジャックと、『おバカさん』のガストンとを比較すれば、すぐわかる。ジャックは神学生でありながら、傲慢な人であり、自分の問題は解決しつくしたと思いこんで自信たっぷりに人を教えようとする。その傲慢さのために、彼は厭味のある人物となるのを避けられないし、また、その死の意味もあいまいになる。ところがガストンの方は、自分の弱さを悟り、素直に告白する。その謙虚さのために好人物となり得、勝利が訪れるのである。他の登場人物についても、同じことが伺える。例えば、『海と毒薬』の野呂は、「これからだって自信がない」と叫ぶが、恐怖を告白したネズミは、まさにそのために殉教者に変わったのである。
遠藤氏は人間の弱さを物語っているか、その描写には、一種の混同があるようにも見える。すなわち、身体の弱さと精神のよわさが不当に混ざっているとも見られるのである。確かに『四十歳の男』の主人公においては、大手術をする病気と、康子との姦通という罪を、明らかに、同列に見ているようである。他の作品でも同様で、『白い人』の「私」の斜視と悪意、『海と毒薬』の看護婦の不幸と生態解剖の承諾、『その明日』の藤五郎の転んだことと「私」の病気、いずれもその感をまぬがれない。しかし、この同一視がはたして不当なものであるか、ということになると、問題は別である。もちろん、病気と罪は異なるし、それぞれの弱さは異質のものでもある。しかし、そこに何らかの繋がりもないとは言えないだろう。むしろ、その関係を追及するのは、身体と精神の統一体としての人間の姿を目指すことではないであろうか。それにこの作家は、病気と罪とが同じものだとは、どこにも言っていない。
区別をしながら、その関係を深めようとする。もつと性格に言えば、病気と罪とが呼応して、病人の弱さと罪人の弱さが互いの説明となり、互いのシンボルとなるのである。
しかもその交錯は、あくまで芸術的な手法であって、作家の自由の範囲を、いささかもはみでるものではない。
これも実は、伝統的な書き方にすぎないのである。一例だけ挙げると、ルオーの「ミゼレレ」は、そのように、罪と苦悩を一新に背負った人間の、両面の弱さを描いている。
ただ一点、以上述べてきたことと相容れないところが、遠藤氏のある作品にみられることがある。それは宿命観である。「宿命」という言葉が、『白い人』のなかにあるし、二人の主人公は、その運命に圧迫されているように見える。『海と毒薬』の中にも、「運命」という言葉こそ出ないようであるが、運命論の色は、特に看護婦の場合など、まだ濃いと言わなければならない。その後の作品では、その色は次第に薄れ、僅かな「仕方がない」が現れてくる程度ある。言うまでもないが、宿命観はキリスト教とは全く合わない。運命の圧迫を覆して、人間に自由の道を拓くのが、キリスト教なのである。しかし、ちょっと触れたように、遠藤氏の作品は、その点で変化があり、進歩があると言えそうである。しかし、ちょっと触れたように、遠藤氏の作品は、その点で変化があり、進歩があると言えるのである。最初の『白い人』では、人間の弱さは定められたものであって、人は、自分に宿命を負わせた不正なる反対者と闘わなければならないと、という見地に立脚していた。しかし、後に、例えば、『おバカさん』になると、人間の弱さは客観的な条件であり、人はその事実を認めた上で、それを乗り越えて豊かに生きる。また更に後の『四十歳の男』では、怨恨は姿を消し、妻の赦し、九官鳥の身代わりによって活路を開くことが、それに代わる。呪われた人の嘆きから諦念へ、諦念から奉仕の心へ、次第に宿命観から抜け出し、明るい人生観へと向かった歩みが、遠藤氏の作品群に認められるであろう。
この作家は、まだ、40代に入ったばかりであり、今後もいくつかの佳作が期待される。作者は何を書くべきかを読者が要求するのは、もちろん筋がちがうが、一言もし許されるならば、ガストンの姿に呼応する日本人の主人公の登場が待たれる、と言っておこう。