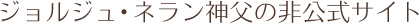『おバカさんの自叙伝半分』私的余聞あるいは余分
支倉 崇晴
日本の教会はどれほど多くを外国人宣教師に負っていることだろうか。私個人とても例外ではない。
私の場合、仏語仏文学を生業としていることもあって、とりわけフランス人司祭のお世話になってきた。仏人司祭と最初に知り合ったのは都下清瀬のサナトリウムで療養生活を送ったときだが、以来多くの個性溢れるフランス人宣教師と出会い、彼らから実に様々なことを学び、深い影響を受けてきた。でも、その中から一人を選ぶとすればネラン師ということになるであろう。帥は『おバカさんの自叙伝半分』を上梓しておられるが、ここではそこには述べられていないことを多少記すことにしたい。帥のあとがきによれば、つまらない話題は避けたので「自叙伝半分」になったそうだが、私自身にとってここに記すことは、つまらないどころか、実に貴重な人生の一コマ一コマなのである。私の思い出の中の師について記すので、話が極めて私的なものになることは予めお許しいただきたい。大学時代、「学生のキリスト教教育を月的とする学生センター」である真生会館に入り浸り、そこでの様々な活動に首を突っ込んで過ごしたが、当時帥はここの住人であった。仏語学習の一助にと、現在京都大学文学部仏文科教授をしている広田昌義を語らって、二人で師にフランス語を教えて下さいとの申し入れをしたときが師との長い縁の始まりである。カミュの小品を教材にこのレッスンは数ヵ月続いた。途中から師の日本語の指南番である早稲田大学の中村明氏が加わった。謝礼は受け取ってもらえず、最後のレッスンが終わったあとビールを御馳走できただけであった。
六十年安保の騒ぎが収まったころ、師はポケットマネーをはたいてキリスト教精神に基づく一般学生向け新聞を発行することを企てられた。「しお」と題するこの新聞作りは残念ながら学生の手には余り、三号までしか続かなかったが、その編集に加わることで帥と毎日のように顔を合わすことができたことは、私にとって実に得難い経験であった。当時私は、のちに師が教鞭をとることになる東大教養学科フランス科の学生であったが、「しお」二号の一面の座談会のために前田陽一主任教授を招くことに成功し、教授を初めて帥に紹介することができた。
当時真生会館に住んでいたもう一人のフランス人であるベルナール・テリアン師(長くパリのサクレ・クール寺院におられたが、本年九月パリのノートルダム・デ・プラン・マント教会主任司祭に就任)は東大教養学科フランス科に出講しておられ、私もベルクソンやクローデルを教室で教わるほか、「テリアン会」といフランス語でディスカッションをするグループを組織したりして大変お世話になった。このテリァン師が帰国の際、後任に師を推薦された。のちにソルボンヌの教授になり数年前亡くなられたオーギュスト・アングレス氏は、当時東京日仏学院長で、東大教養学科でも教えておられた。帥と同郷のリョン出身である氏は、よく師のことを「典型的リヨン気質」、「抹香臭さゼロ」と評しておられたが、やはりテリァン帥の後任に師を推薦された。こうして師は東大で教え始められることになり、学生だった私は前田主任教授の命により師が履歴書を書くのを手伝い、それを大学当局に届け、帥の授業にも顔を出した。
仏文大学院に進学した夏、私は旧鹿沢温泉で宿の跡取りの家庭教師をするために一夏中逗留することになった。ある日この宿に前触れもなく師が来られ数日滞在されたので、一緒に温泉に入ったり、付近を散策したりした。一日山向こうの上田市に降りて行かれた師は、お土産だと言って、頼んだわけでもないのに爪切りを下さったりした。
秋になり山を降りたが、修士論文のめどはつかず、身辺の人間関係に悩んだりしていた私は、一つの転機を迎えるきっかけになるかもしれないと思い、フランス政府給費留学生試験を受けることにした。出願書類に添付する推薦文を師は熱を込めて書いて下さった。この推薦文に込められていた師の期待にその後全く応えていないことは、私にとって重いしこりとなっている。
こうして翌夏渡仏することになった私は、事の弾みでフランス科の同級生と結婚することになった。媒酌の労は前田陽一教授が取って下さり、妻となる同級生も師の授業に出ていたので司式は師にお願いした。師も非常に張り切られ、式中高逼な説教をされたのには面はゆい思いがした。
三年半余りの留学中、師は数回フランスに来られた。一度はパリ南郊の間借りしていた家まで来ていただいた。途中の電車の中で師は「この電車は日本のより速いな」と言われた。師の言われることに何かと反抗し楯突く性癖のあった私は、内心同意しながらも「そんなことはありませんよ」と愛国心を発揮したりした。この訪問の際師はお土産代わりだと金一封を下さった。日本の習慣に従ってその場では開封せず、あとで開けてみたら何と五○○フランも入っていた。当時私がフランス政府からもらっていた給費が月四八○フランの時代である。異境で妻子を抱えてアルバイトに明け暮れ、近く二人目の子供が生まれようとしていた身には涙が出るほどありがたかった。でも、フランスの習慣に従ってその場で開封していたら、痩せ我慢を張って突き返したのではないかという気がする。
帰国して数年後の一九七三年から私は東大教養学部に勤務することになったので、師が定年で非常勤の職を退かれる一九八○年までの七年間は、いわば師の同僚であった。師は教壇に立つのと同時に、カトリック研究会の後身である聖書研究会の面倒も見ておられたので、師の依頼の下に学生が私の研究室に教室借用順へ判を押してもらいに来ることもあった。
一九八○年二月に前田陽一教授はソルボンヌより非欧米人学者としては初めて名誉博士号を授けられた。そのお祝いの会をしたいと申し出たところ、前田先生は自分のためだけなら断る。定年退職されるネラン先生を送る会の添えものとしてなら出席するとのことで、二月二十九日に国際文化会館で両先生記念パーティーが開かれた。師は赤い陣羽織に赤い帽子姿で登場され万雷の拍手を浴びられた。前田先生は、サン・シール士官学校出の師のことをよく『赤(軍服)と黒(僧服)』なんだと言っておられたが、このとき、師も還暦を迎えて本卦がえりされたのかなという幻想に一瞬とらわれたものである。教師の間で師は「大僧正」と呼ばれていたので、羽織の赤色は軍服の色よりはむしろ枢機卿服の色だったかもしれない。
このほかにも師をめぐる思い出は尽きない。妻に洗礼を授けていただいたという恩義などもある。従って、「エポペ」の計画が公になった際、直ぐ様貧者の一灯を投じて生まれて初めて株主になったことはいうまでもない。
(『カウンター越しの物語』より)