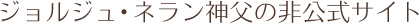概念のキリスト、隠喩のキリスト
キリストが生きていると信じるのはキリスト教の基礎である。そして、生きているキリストは二千年前十字架上で死んだイエスにほかならない。だからキリストの復活が信仰の核心になる。その復活したキリストを信者は信じ、愛する。パウロの言う通り「キリストが復活しなかったなら、私たちの宣教はナンセンス」である。
ところで、生きているキリストは私たちの目には見えない。この事実を信仰でどう表現すべきかという問題が出てくる。キリストを愛する信者は当然キリストを語ろうとするとき、地上のイエスの姿と同時に復活後のキリストを描きたいと思う。ところが、私たちは誰も復活したキリストを体験したことがない。
そこで、一つの考え方が生まれる。福音書の描き出すイエスを常に"神の子"とみなすことである。ある角度から見ればそれは正しい。しかし、「神の子は湖畔を歩いていた」とは言わず「イエスは湖畔を歩いていた」と言う。また、「イエスは"神の子"だから将来をすべて見通していた」と言うことは許されない。将来を知る者はもはや人間ではないからである。
イエス・キリストは神の子であると同時に真の人間である。換言すれば、キリストは神性も人性も備えているが、この両者は混合されてはいない。福音書のイエスを、ただちに"神の子"と見るのは誤解を招くもとになる。
キリストが十字架上で死んだこと、三日目に復活したことを、ひとまず宣言することはできる。それに誤りはないが、「何かをしたこと」を述べるのは信仰の核心をそれることになる。信じ、愛するのは、相手のしたことではなく、キリスト自身なのだから。
したがって、キリストを語るためには、概念やカテゴリーを捨て、比喩や隠喩による方法が多くとられる。「神の子」という表現も隠喩である。これは人間の世界における父と子の関係そのままではない。隠喩はあくまでも隠喩である。抽象的な概念では、キリストは神性にあずかると言える。しかし、これは空疎な表現である。ヨハネの強調する「父は子を愛し、子は父を愛する」という父子の絆を表現することはできない。キリストを語ろうと思うなら、隠喩を使い、それを跳躍板として利用して超越的なリアリティーの世界に飛び出さなければならないのである。
新約聖書は旧約のカテゴリーを用いる。たとえば、イエスはメシアである(もっともメシアのギリシア語は「キリスト」であるが)。しかし、イエスは当時のメシアのイメージにおさまりきらない。メシアの死と復活は期待されていなかったのである。同様に、イエスは「王」と呼ばれているが「私の国はこの世には属していない」と自ら訂正する。また、預言者とも呼ばれているが、預言者の中の預言者である洗礼者ヨハネをはるかに超えている。これらのカテゴリーはイエスに当てはめると、古い革袋のように破れてしまうのでる。
神の子の栄光を強調するヨハネ福音書で、イエスは「私はブドウの木、あなたがたはその枝である」と言う。これはまさに隠喩であり、含蓄のある隠喩である。その深い味わいはキリスト論の常套の命題を凌駕している。
歴史を超えるキリストを歴史家は理解できない。概念を弄ぶ神学者は生きているキリストとの交わりに人々を誘い入れるまではいかない。しかし、隠喩を駆使する詩情豊かな信者はキリストの心に導くことができる。愛は隠喩をもって語るからである。
Gネラン(1995). 季刊エポぺ 39号