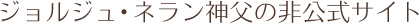巡礼の旅から(3)ゴッホ編
見田 栄征
ネラン神父が「美について」で「ゴッホ」と名前を出した時、そこに何を見ていたのか、知りたくて、ゴッホの終焉の地を訪ねてみた。
午前零時、羽田から大韓航空で仁川空港へ。
乗り継ぎで五時間待ちして、トータル20時間かけてパリへ。
仁川第二空港からのヨーロツパ線は、それでもエルフランセで、CAは皆さん年配の女性であったが、親切このうえなく、ワインも飲み放題。
長時間のフライトは、ワイン好きの私にとっては全く気にならない。
料金の安さと、反比例するフライトの長さは、逆に超魅力的ですらあった。
直前に、シャンゼリゼでテロがあり、パリの中心街に行くのは危険だったので、郊外の東駅の駅前に拠点のホテルをとる。
パリ東駅は北駅と隣り合わせで、ランスへは東駅から北東へ、ゴッホが眠るオヴュール・シュル・カワ-ズへは北駅から北西へ直通。
久しぶりのバリ。
駅で切符を買うのに手間どる。
駅構内には、肩に自動小銃を下げた兵士が巡回し厳戒体制。
一人旅の不安を抱え、鈍行に乗る。
電車のシートはやたらカラフルで、市街を走るチンチン電車。
北西へ30分も行けば、もうそこは田園地帯。
フランスが農業国だということに、すぐ納得する。
乗り継ぎもスムーズにオヴュール・シュル・カワ-ズの駅に着く。
(二)
「5月17日の朝、パリ到着。三日滞在。
彼は五月二十一日にオヴュールにたった。」
(ボンゲル夫人 小林秀雄「ゴッホの手紙」p164-165)
私が、訪問した、ちょうど同じ季節に、ゴッホはアルルから移ってきた。
「オヴュールは実に美しい。
とりわけ美しいのは、近頃次第に少なくなって来ている古い草屋根が沢山あることだ。
本当に田舎だよ。」
(ゴッホの手紙NO635 小林秀雄「ゴッホの手紙」p165-166)
驚くことに、オヴュール村は、この130年前のゴッホの文章通りであった。
「時が停止している」とさえ感じる。
「七月二十七日午後、オヴュールの丘で自殺の現場を見た人はいない。
二十九日の午後一時半、ゴッホは死んだ。
最後の言葉は『来てもう死にそうだ』という言葉だった。
三十日、遺骸はオヴュールの共同墓地に埋葬された。」
(小林秀雄「ゴッホの手紙」p176)
ゴッホのオヴュールの僅か二か月余りを
「ナザレのイエス」の「エルサレムの受難の道行」に比することは
ネラン神父の「宣教」を「聖パウロの宣教」に比する
「ネラン教のパラノィア」と同じであろうか?
ネラン神父が、「キリスト教は宗教ではない」と言う時、
べつの意味でも、何年後かに自分の死後に起るであろう自らの「神格化」に対し、
警鐘を鳴らしていた、とみるのは考え過ぎか?
カフカは、生まれつき<絶望>を内在し、ゴッホの<絶望>は、無意味な死。
しかし、
死後、ゴッホは、<画家として復活>する。
(三)
オヴュールの駅から歩いて数分の所にゴッホが下宿していた建物は、すぐにあった。
建物は建て替えられ、一階の居酒屋は資料室になっていて、ゴッホの部屋は二階で、室内は当時のままに保存されていた。
そこの裏道を抜けて、ニ・三百メートル田舎道を行くと、あのなじみな『オヴュール教会』が現れる。
(2)『オヴュール教会』
「僕がニューネンで描いた古い塔と墓地の習作とほとんどそっくりな感じだが、ただ、今は色がおそらくもっと表現的に豊かになっている。」
(ゴッホ書簡W22 1890年6月初め妹ウィル宛の手紙)
実際の教会は、建物も大きくて、荘厳な造りをしていた。
ゴッホの絵は、教会の建物が傾いているように見え、屋根も歪んで見える。
絵を見るものを、何故か不安にする。
「ニューネンで描いた古い塔と墓地の習作」から比べれば、確かに、色の使い方に画家として、十分な進化が見て取れる。
そこから少し裏に歩いていくと、もうそこは、あの『麦畑』。
我々が、ゴッホの絵でお馴染みの麦畑がまさに絵のごとく、目の前一杯に拡がるのである。
ゴッホはこの時期に麦畑を二枚別々に描いている。
(3)『鴉の群れ飛ぶ麦畑』
「群れた麦畑の上を黒い鳥が舞う。道は3つに分かれて広がっていく。主題といい荒々しい筆蝕といい、非常に劇的。終末的な印象を与えるせいか、『最後の審判』を描いた絵とする解釈さえ出されたことがある。」
(西洋絵画の巨匠②ゴッホ 小学館 p113)
(4)『荒れ模様の空の麦畑』
「それら(二点)は荒れ模様の空の下の広大な麦畑で僕は思い切って悲しみや極度の孤独を表現しようとした。まもなくみてもらえると思う。というのもこれらの絵は言葉では言えないもの、田舎の健康で力づけてくれるものを、おそらく君たちに語ってくれるだろうとおもうからだ。」
(ゴッホ書簡649)
二枚のは同じ麦畑を描いているのに、まったく異次元な世界が拡がる。
「それら(二点)は、悲しみや極度の孤独を表現した」といってはいても、一方は、空は荒れていても穏やかに平凡なありふれた一日であるのに、もう一つは、鴉(カラス)が低く飛びかい、見るものに異様ささえ感じさせる。
確かにそれは、<終末>さえ思わせる。
この絵が、ゴッホの絶筆とする、小林秀雄の予測もうなずける。
そして、麦畑を20~30分も行くと、そこは、ゴッホの眠る共同墓地であった。
墓苑は広大で、探すのに手間取る。
弟テオと仲良く並んでの墓は、生前のゴッホの貧困生活が嘘のように、立派で、それでいて静かな時の流れを感じさせものであった。
オヴュールの駅に降り立って僅か3時間後に、私は再びあの『オヴュール教会』にいた。
教会の前に唯一あった、小さなレストランのオープンテラスで朝食兼昼食。
時間はたっぷりある。
つぎの駅まで2時間以上かけて、ブラブラ歩いてみる。
途中にも、いくつかのゴッホゆかりの場所があり、特に「ガシュ医師の家」は当時のまま解放されていた。
(1)『医師ガシュの肖像』
「他のどの仕事よりも僕の情熱を掻き立てるもの、それは肖像画。現代の肖像画だ。
僕は一世紀後、その時代の人に幻のように見える肖像を描きたい。」
(ゴッホ 書簡W22)
この絵は、ゴッホがオヴュールにきて、最初に描いた絵であると思われる。
全体に左に傾いており、やはり見るものを不安にする。
シャボンウァル駅は無人駅で、パリ行の電車を、駅のホームのベンチで一人2時間待つ。
夕方5時過ぎ、取り敢えず、何事もなく電車は無事、北駅に着いた。
(四)
ネラン神父は、ルオーと同じく、ゴッホを取り上げたものの、一か所であった。
しかもルオーについては他でもあれだけ語りながら、ゴッホについては、名前だけ。
内容には触れていないことに特別な意味があるのか?
欧州人にとって、ゴッホは画家として、あえて取り上げるのに一般的であるのか?
逆に、浮世絵にはまり、「日本人」になりたいと希求したことで、日本でもゴッホのことは一般的に誰もが知っている画家だと、思ったのか?
そうではないであろう。
やはり、そこにはゴッホの生い立ちと彼の画業としての特異があった、のだと思う。
ゴッホは、父が牧師で、自らも牧師を目指していてラテン語ができず牧師になることを諦め、その後、伝道師を目指すも、異常なまでの献身のため解雇される。
ゴッホのその後の画業を中心とした一生も、この「神の痕跡」との「格闘」であったことを、知っていたであろう。
そして、一般的に、絶望の画家と言われる彼の絵の中に、確かな「神の痕跡」を見ていたのではないか?
小林秀雄がどんなに「ゴッホ」を論じ、その<絶望>を語ったとして、そこに、「神の痕跡」を見ない限り、ゴッホの絵を、人生を正しく解説したことにならない。
小川国男は、「神の痕跡」を「聖書」という言葉に置き換えてみてはいるが、どこまで、それを掘り下げてみているかといえば、疑問が残る。
「神の痕跡」といえば、遠藤周作の<絶望>のほうが遥かにわれわれの胸を打つ。
たとえその<絶望>が、遠藤が作家を続けるために生涯身にまとった「背丈に合わない仮縫いの洋服」であったとしても。
一旦、「神に捉われ」その「痕跡」を消すために、夢中で絵を描き続けたゴッホ。
彼は死ぬまで「神の痕跡」と戦い、力つき、「偶然の死」を受け入れる。
ゴッホの<絶望>は、「神の痕跡」から逃れ、そのために絵を描き続けながら、結局、そこから生涯逃れえなかったこと。
ゴッホにとって、死は<絶望>ではなく、自分からの<解放>ではなかったか?
現在、われわれは、ゴッホの絵、特にオヴュールの最後の4枚の絵に「美の内在」をみる。
(2017年4月 パリ オヴュール・シュル・カワ-ズにて)
< 註 >
『美について』
「(あるいは)ゴッホの作品は彼が生きている間は、美しくなかったという訳だ。」
「かくして、美は超越的なリァリティーとして、作品に内在するのである。」
『ゴッホの死について』
ゴッホは一般的には自殺したことになっているが、最近の研究では、青年にピストルで撃たれて死んだのではないか、という他殺説がでてきている。
ピアラ監督の映画『ヴァン・ゴッホ』でも、実際に自らを撃つシーンはなく、
「-----その間、ヴィンセントの内面で、自殺に追い込まれるどんな葛藤があったのか、謎として遺された。」(「モーリス・ピアラ読本」より)
『ネラン教のパラノィア』
いかに自分がネラン神父の一番近くにいたかをやっきになって主張して、個人的係わりを勝手に自己修正することを平気で行う、その行為がオカルト教団の生成基盤であり、「ネラン教のパラノィア」だという。
同時に、ネラン神父の著作の出版権をめぐっての争いをも含めて「ネラン愛が強すぎるため」という。(寺田氏談)
確かに、ネラン神父の周りに集う人々がそのことにどれ程自覚的か?
私を含めて。
『キリスト教は宗教ではない』
「最後にもう一つの証拠を挙げておきたい。マルキシズムは宗教でないと一般的に認められている。しかし、それは、キリスト教に一番近い考え方をしている。むしろキリスト教の異端とさえいえる程に」
(ネラン神父『お茶の実』6巻24号、25号 1965年10月25日)
50年以上経って、マルクス主義の評価も変わってきてはいるが、基本がヒューマニズムであるのだから、その点では、キリスト教を源流にもつのである。
ネラン神父の根底には、ティヤルド・シャルダンの思想があり、キリスト教には、科学的・合理性がある、と言っているのであるが、確かに現状の宇宙物理学の進化・発展は、遥かにネラン神父の予測を超えている。
とはいえ、誤解を恐れず言わせてもらえば、ネラン神父が本当に伝えたかったことは、あくまでも、「ナザレのイエスの復活」は事実であり、宗教ではない、と。
ローマカトリック教会を頂点とする「キリスト教」は宗教であったとしても。
『ゴッホの絶筆』
「-----彼が自殺直前に描いた麦畑の絵。-----色は昨日描き上げた様に生々しかった。
------この色の生々しさは、耐え難いものであった。これはもう絵ではない。彼は表現しているというより寧ろ破壊している。
カンヴァスの裏側には『絵の中で、僕の理性は半ば崩壊した。』(死後発見された未投函のテオ宛の手紙)という当時の手紙の文句が記されているだろう。」
(小林秀雄 『近代絵画』p102)
『小川国男の<聖書>』
「-----ゴッホの写実主義の軸は<聖書>ということになる。
-----<鴉の飛ぶ麦畑>も異常な絵といってもいいかもしれない。
-----まれな悲劇性で私たちの胸を打つ。そしてこの悲劇の相貌の原型もまた<聖書>の中に見て取れる。」
(小川国男『ゴッホの宗教性』「総合教育技術」昭和53年6月p123~p124)

オヴェールの駅前 
教会へ続く道 
ゴッホの墓 
教会(一部)