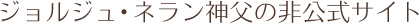『キリスト論』

< 目 次 >
- 序論
- 問題の選択
- 信仰の立場
- 学問の立場
- 人の子
- 問題をめぐって
- 旧約の背景
- 「人の子」出所一覧
- 試金石の箇所
- 来たるべき「人の子」
- 受難の予告
- 地上の「人の子」
- キリスト論上の結論
- マルコ
- 序論
- 難問
- 一人の著者
- マルコのイエス像
- 編集と資料
- メシアの秘密
- 奇跡において
- 悪霊に対する沈黙の命令
- 弟子に対する沈黙の命令
- 譬えの論理
- 弟子の無理解
- 復活とその前触れ
- 復活の告知
- 『死-----復活』
- 神の子
- 受難の記述
- 『受難の義人』
- narrative の問題
- 香油注ぎ
- 晩餐
- ゲッセマネの祈り
- 全議会の判決
- 夜の裁判の歴史性
- 嘲弄の場面
- 「エロイ エロイ---------」
- 百卒長のことば
- 権威あるイエス
- 罪をゆるす
- 「私に従ってきなさい」
- 教え方
- 論争
- 感嘆の声
- 悪霊祓い
- 奇跡
- イエスの弱さ
- 結論にかえて
- 序論
- パウロ
- パウロの生涯
- パウロの『福音』(ロマ1・2—4)
- 週末のキリスト
- 生命たるキリスト
- キリストから信者へ
- 信者からキリストへ
- 普遍性
- 万物の支配者
- コリ前15・24—28
- ロマ8・19—22
- ピリ2・9—11
- ヒリ3・20—21
- コロ1・15—20
- エペ1・10
- エペ1・20—23
- 御子
- ヘプル人への手紙
- 手紙の概況
- メデキゼデク型の大祭司
- 兄貴としての大祭司
- コーチたるイエス
- 先在
- 御子
- 人間性
- ヘブル語は我々に何を教えるか
- ヨハネ
- 序論
- 福音の編集
- ヨハネにおけるシンボル
- イエスの時
- 12・23—27 の解釈
- カナの婚礼
- 栄光
- 父をドクサする
- 子がドクサされる
- 地上のドクサ
- 御子のドクサ
- 真理
- 啓示
- イエスは心理を語る
- イエスは心理のために証言する
- 真理に満ちたイエス
- 真理であるイエス
- 真理の御霊
- 父と子
- ヨハネ福音書の序言
- 先在
- 序論
- アンチオケのイグナチオ
- アレイオス
- カルケドーン公会議
- エペソ公会議
- エペソ『盗賊会議』
- カルケドーン公会議
- カルケドーンの信経
- レオのキリスト論
- カルケドーンの今日的意味
- 現在の視座に立って
- 不可欠なキリスト論
- キリスト論の森
- 受肉について
- イエスは誤ったか
- イエスの死の意味
- 概念か像か
- キリスト論における概念
- ミステールである対象
- キリスト論における像
- 時間におけるキリスト
- クルマンの立場
- 時間把握
- <何かするための時>
- narrativeにおける時間
- 典礼の時間
- 中心を成す復活
- 今日的キリスト論
- あとがき
< 序 論 >
手ごろな厚さの「キリスト論」を書こうとすれば、広大な分野からいくつかの点に絞ることが必須の条件になる。本書は、問題の選択、その扱い方の選択、および、その精密さの度合の選択、解釈の選択といったさまざま選択を経て書かれている。しかし、それでも、なぜあの点を差し置いてこの点を選んだのか、しいう理由を述べるスペースまでは全く残っていない。ただ、筆者の関心の強さという点のほか、日本人の読者にとって有益であるという点もその選択基準の一つになった、ということだけは書き添えておこう。
もっとも心苦しく思いながら割愛したのは、何といっても、キリストの復活という問題である。これは、忠実に扱おうとすれば、それだけで優に一個の分量になる。そのため、やむを得ず割愛したわけである。けれども、キリストの復活に対する自分の立場は、テーゼという形ででも明らかにしておかなければなるまい。
まず、キリストが復活したことがほんとうだとする。ほんとうだから、それを「史実」と呼んでいいかどうかは、「史実」の定義次第である。弟子たちがキリストの復活を信じたという信仰それ自体は史実と一般に認められているが、それから問題が始まる。弟子たちの信仰が錯覚でなく正しかったとすると-------本書はその立場をとっているが------信仰の対象である復活は史実になるのかどうか、という問題が出る。「史実」をこの世の三次元の現象に限るならば、復活は史実だといいにくい。しかし、「史実」という言葉が、確かに起こった出来事を指すのだとすれば、復活は史実だということになる。したがって、本書では、「史実」の定義の問題を差し置き、キリストの復活はほんとうだという立場をとった。(復活の歴史性に関しては、Pannenbarg の見方に大体は従うつもりである)。
復活は実際に起こったことなので、弟子の主観的な体験を表すだけでなく、それはまた、イエスの身に起こったことでもある。イエスは復活によって時間と空間という次元を超えて存在してゆく、と言える一方、復活した者は死んでいた人間たるイエスなので、その点から見れば、ある時にイエスは復活した、とも言える。換言すれば、超歴史的な状態への変化としての復活は、イエスの歴史的な存在と断絶するというよりも、イエスの地上の生涯を絶対化することなのである。したがって、復活はキリスト教の基礎であるばかりでなく、イエスの生涯に決定的な意味を与える出来事でもある。
次に、復活したキリストが現れたことを「出現」と呼んでおく。それは、イザヤ書6章に見られるような神のTheophany と区別するためである。復活したキリストは目にみえない存在なので、その出現は全く客観的な現象------たとえば、カメラで写せるもの-----だというわけにはいかない。しかし、まぼろしのような全く主観的な現象(例えば ophtasia コリ12・1)とは違う。出現にある程度の客観性を認めなければ、弟子の信仰は不可解なものになる。
そもそも、イエスがほんとうに復活したと認めるならば、彼が弟子を信仰へ導くために、きわめて例外的ではあるが、実際に現れたということも、あながち認めないわけではない。復活に対する本書の立場をごく簡単に述べると、以上のようになる。
本書は神学論である。すなわち、信仰の立場に立ってキリストを研究するのである。そういう立場の性格をもう少し説明しておこう。
- (1)信仰を前提とするので、本書は読者を、信じる方向に導くというようなことを目的としない。イエスが神の子であることを証明しようなどとは思っていない。そういうことよりも、イエスが神の子であるという告白が何を意味するかを研究するのである。
- (2)本書は信仰の立場をとるが、だからといって何らかの特別な研究方法をあらかじめ用意するというようなことはしていない。本書は結局、キリストに関するいくつかの文献を研究することになるが、その研究のためには一般的な文学研究の方法しかない。一つのテキストの意味は、そのテキストの分析、あるいはその文脈からのみ出るのである。
- (3)プラトンを理解するためにはプラトンの弟子の立場をとり、マルクスを理解するためにはマルクスの弟子の立場をとらなければならない。これは研究者として当たり前態度である。キリスト論を書くためには------イエス自身は何も書かなかったので--------キリストについての文献を研究する。その文献の著者たちはキリストを信じていた。研究者も同じ立場をとらなければならない。したがって、信仰の立場をとるのはキリストを学ぶ学問の性格上も必要な条件である。信仰を述べるテキストを研究する時に、研究者が信仰の立場をとらなければ、それだけですでにこの学問上では落ち度となる。
- (4)信仰の立場をとるからといって、特定の研究方法を採ることにはならないが、それは常に全体の理解へ向かう道を先導する。具体的な例をあげてみよう。キリストに関するテキストを研究するときに、パラドックスもしくは矛盾にぶつかることがよくある。信仰を度外視、それは謎のようなものとしか考えられないし、その著者は阿保以外のなにものにも見えない。しかし、著者のもつ信仰の立場をとるならば、彼らが超越的なリアリティを表現するためにパラドックスを使ったということがわかる。少なくとも、そういう仮説がすぐに浮かんでくる。もちろんその仮説を文学研究の方法で確かめるという課題は残っている。
- (5)研究の立場としての信仰というのは、キリストに関する文献を書いた著者たちの信仰のことである。この著者たちの信仰は必ずしも一致してはいない。否、文献はむしろ異なった信仰を表現しているのである。この史実は本論に深くかかわるので、改めて考えてみることにしたい。
キリスト論とは「イエス・キリストとはどういう者か」という問いに答えるものである。最後の章で指摘するように、その答えはいろいろある。本書では、キリストに関する文献を研究という答え方を選んだ。すなわち、マルコ福音書、ヨハネ福音書、カルヶドーン公会談などの提供するキリスト観を把握しようとした。それは、あらかじめ一つの信仰告白を掲げてそれを文献によって正当化するのではなく、文献の蔵するキリスト像を学問的な方法に基づいて追求するのである。この態度からふたつの重要な結果が出る。それはまず、本書が教義的キリスト論を述べるよりは、イエス論を展開する、もしくはイエス像を描き出すということである。もう一つは、各文章から出てくるキリスト論はそれぞれ異なっているということである。すなわち、イエス・キリストは一人しかいないのに、キリスト像がいくつもある、という奇妙な事実にぶつかる。もしどの文献もすべて全く同じキリスト像を提供するのなら、改めてキリスト論を書く理由がなくなるともいえようが、このように、さまざまなキリスト像が共存することになると、そのうちどれがほんとうのキリスト像なのか、という問いをどうしても避けて通るわけにはいかない。この場合、それらのキリスト像のどれか一つを基準とする、ということももちろん考えられるが、しかし必ずしもその一つを選ばなければならないというはっきりした理由があるわけでもない。あるとしても、それはとうてい学問上の理由とは言えない。また、ある一つのキリスト像を基準にとれば、もうその他のキリスト像を追及する必要性はなくなるのではないか。
やはり、異なったキリスト像を同時にまた同等に受け容れるべきであろう。そうすれば、どういうふうに唯一のキリストが異なったキリスト像として描かれてしまったのか、という問題が残る。異なったキリスト像から唯一の真のキリストのイメージを復元することは、学問のレベルを超える課題であろう。信仰の眼のみがさまざまなキリスト像をキリスト自身に統一することができるのである。そこで、筆者自身の意見を述べてみよう。以下はでてくるキリスト像はそれぞれ異なってはいるが、しかし、すべての像がその人物のイメージを忠実に伝えていると同様に、異なったキリスト像は、異なっているからこそ、忠実にまた豊かに真のキリストを描き出している、と言えるのである。異なったキリスト像が存在することは、キリストの「無尽蔵の富」(エペ3・8)を多少とも展開し、また、キリストは知り尽くせないということを物語っているのである。
しかし、異なったキリスト像を唯一のキリスト像に属することができず、例えばマルコのキリスト像とカルケドーンのキリスト像とは相容れないと考える読者もいるかもしれない。
その点は信仰上の問題であって、論争すべきところではない。本書は学問的な見地に立つつもりなので、学問上の問題を取り扱う。それは、とりもなおさず、キリストに関するいくつかの文献におけるキリスト像を把握することである。
本書の用語に関し、次の二点を断っておきたい。まず、キリストに関して「神性」という語を慎重に使った。 この語は新約聖書には出てこないし、神の〈本性〉を論ずるものとして一定のキリスト論に属する用語だからである。
次に、〈ミステール〉という語を用いたが、これはフランス語の Mystere のカナ書きにすぎない。その意味は「生命の神秘』における「神秘」というのに近い。が、「神秘」という語を使うと、神秘主義などの連想を恐れがあるので、それを避けたわけである。
参考文献は最小限に絞って掲げた。選んだのは(1)新しく、また、豊富な参考文献リストの載っている、すでに定評のある研究文献(2)本書に引川した研究文献(3)忘れられがちだが価値があると思われる研究文献である。これらの参考文献の中に、読者は本書の立場を補充するデータ、あるいはその反論を見出すであろう。
なお、日本語で害かれた『聖諏語句大辞典』(教文館一九五九年)および『聖害思想事典』(三省堂一九七三年)という名著について改めて紹介する必要がないであろう。
< あとがき >
この『キリスト論』を執筆するきっかけになったのは、一九七四年に真生会館で指導した『オメガゼミ』という神学研究会である。当時のそのゼミはきわめて活発な意見の場であった。
しかし、それでも、その成果が本書に影を落としているものと言えば、各章の表題ぐらいのものである。つまり、それは以後あらためて、全面的に研究し直した結果、本書が生まれたのである。
この本のための原稿を書き始めたのは、私がまだ真生会館にいたころのことである。が、理事長職で多忙をきわめ、なかなか捗らなかった。一九七六年の秋に私は真生会館を去って、この聖マリア学園に移った。静かな環境で、しかも、キリスト教教育修士会のメンバーの暖かい友情に包まれながら、この難事業もここにようやく完成に漕ぎつけたわけである。
三十年ほど前に、私が初めてローマに行った。その折S.Giogio in Velabro という教会を訪れた。その教会の名誉主任は↑ハチカンの研究聖省の責任者たる一人の枢機卿であった。
教会の壁に彼の紋章とそのモットーが記されていた。名前のほうはあいにくと忘れてしまったが、そのモットーのほうは肝に銘じていまだに覚えている。それは
semper paratus doceri
「教えられる心構えをいつも」とでも訳したらよかろうか。