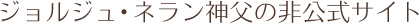仏訳者から見る「鹿鳴館」
二十年前、私は「鹿鳴館」をフランス語に訳した。その理由はただ一つ、「鹿鳴館」が好きだったから。どれほど三島がフランスの豊かな劇文学に触発されたのかはわからないが、フランス人である私は、「鹿鳴館」ロマン派-----musset の劇を思わせる------に属し、それらの作品中でも傑作であると痛感している。
ドラマが半日の間に集中しているという点からみて、また筋の完全な統一性からみても「鹿鳴館」は古典の規範にあてはまっていると言える。さらに、アクションヲ控えた中で交わされる言葉は極めて制裁を帯びて居る。
対話の多くは観客に事情を知らせる語りではなく、そこでは、不本意な決断をさせるところまで相手を追い込む攻撃精神が発揮される。登場人物相互の言葉の戦いが悲劇信仰の原動力になっている。
部隊の人物は激しい感情に動かされている。彼らを通して愛と憎しみ、信頼と裏切り、政治と理想が互いにせめぎあっている。そしてそれぞれの人物は割り当てられた感情を擬人化し、与えられた像から逃れることなく行動し続ける。
しかし、朝子の場合は違う。主人公朝子は相反する多様な心情に駆られている。過去の日本趣味を守りながら、新式の西洋を受け容れる。清原への愛を元のまま保つ一方で、久雄のことは忘れている。夫に対して、冷淡さをお互いの夫婦の装いでつくろう。同時に彼を裏切ることを恥じる気持ちも残している。
こうした朝子の緊張に張る心の動揺は観客を感動させる。
日本の文学を多少知っているフランス人の友人はヨ鹿鳴館」の結末は甘すぎる。朝子は自殺させるべきだった」と私に言った。なるほど自殺こそこの悲劇の必然的な終幕と見られる。
しかし、三島は別な意図を持っていた。彼は「鹿鳴館」で巧綴な奢侈と惨い残虐が相い伴っていること、否、前者と役者が表裏を成しているという光景を描き出したかったのである。それがため、~態勲な言葉は鋭い刃を隠している。殺し屋は燕尾服を着て、金メッキをほどこした舞踏場で踊っている。その豪華な世界と妥協した朝子は、自分の悲しみを微笑で覆ってワルツを踊り続ける。
今度、村松英子さんが朝子を演じることになる。この才能豊かな女優が生気の躍動している朝子を登場させることを私は期待している。
ネラン神父自筆にて「村松英子主宰「サロン劇場」公演 二〇〇三年七月十八日~二十二日