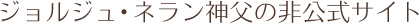キリストとはどういう方か
クリスチャンとは、キリストを信用し、キリストに従う者である。そのクリスチャンに「あなたはキリストをどう見ているか」と聞きさえすれば、キリストはどういう方かという問いに対する、ある答えは得られるであろう。しかし、その答えは、そのクリスチャン自身のキリスト観であって、その人個人の見方にすぎないかもしれない。はたして、すべての信者が統一した答えを示すであろうか。たとえ、信者がみな、キリストは神の子であると告白していても、実際にそうであるかどうかという問題は依然として残る。したがって、キリストがどういう方であるかを知るのに、信者個人のキリスト観を問うのは適切な方法ではない。
問題は、キリストはどういうふうに見られるかではなく、キリストはほんとうにどういう方であるかなのである。それは、キリストに関する文献である新約聖書を研究すればわかる。そこで、便宜上、「神性」ということばを使うことにする。「神性」は、新約聖書にはないが、結局、問題はキリストが単なる人間であるか、それとも神性を有するかということである。
一口に言えば、新約聖書はキリストの神性を主張するとは言えるが、新約聖書はキリストの復活後に書かれたので、キリストの”高拳”は、在世中のイエスの言動を伝える文章にも影響したことは否定できない。福音書には、高拳されたキリストの光が投じられているのである。その結果として、新約聖書に見出されるのは、イエスの歴史的な姿よりも、初代の信者の信仰である、ということになりかねない。しかし、一方、福音記者は忠実に出来事を伝えたかったに違いないし、それに、事実そう努めなかったという証拠もない。共観福音書では、キリストの神性がそれほど明らかに出てこないということが、むしろ、福音書の信憑性をましている。
ともかく、新約聖書全体におけるキリストの神性という点については、次のことをよく考えなければならない。すなわち、キリストの復活(高拳)以前にはキリストの神性が隠れていて、復活そのものがキリストの神性を顕した、ということである。新約聖書のすべての著者にとっても、教会全体にとっても、キリストの復活は決定的な真実であった。この復活は、イエスの地上での生涯を解く鍵になったし、キリストの神性を告白することに導いたのである。
共観福音書の文章から、キリストの神性を結論として引き出すことができるかどうかは明らかでない。たとえば、その福音書では、キリストは奇跡を行うが、それなら神の遣わした人(預言者=聖人)でも行う。キリストは権威をもって教えるが、キリストがその点でモーセにまさるにしろ、それはやはり神性にあずかることとは違う。キリストはメシアであるが、ユダヤ人の待ち望んだメシアは神性を有する者ではなかった。また、新約聖書の伝える出来事全体を旧約の希望の成就としてだけ見るならば、キリストの神性は現れない。
一方、イエス自身が自分についてどう考えていたかは、共観福音書によって決めがたい。神学者はキリストの自意識という問題を取り上げるが、福音書には「わたしは神の子である」といったことばは出てこない。それよりも、福音書は人間なるイエスを描き出している。歩く人、語る人、食べる人、疲れる人、泣く人、怒る人、祈る人、誘惑される人、恐れる人、苦しむ人、死ぬ人、そういう人間らしい人を。そして、それはイエスが真の人間であることを示すためには貴重な史料である。
しかしながら、共観福音書は、二つの重大なことを伝える。一つは、キリストの復活である。これについてはすでに述べた。もう一つは、イエスはつねに神を「わたしの父」と呼んでいることである。これについてはマタイ福音書の七・二一、一〇・三二ー三三、一一・二五ー二七、一二・五〇、一五・一三、一六・一七、二七、一八・一九、三五、二〇・二三、二五・三四、二六・二九、三九ー四二、二六・五三で確認されたい。
この二点を深く考えるとき、キリストの神性は当然の結論になるのである。
共観福音書を別にして、新約聖書はどこでもキリストの神性を教えている。もっとも、「神性」ということばでは出てこないが、別の言い回しでそれが表現されている。キリストを指すために頻繁に(数百回)使われていることばは「主」である。原文ではKyrios(冠詞があったりなかったりするが) であるが、これは旧約聖書では神自身を示す。したがって、それをキリストにあてはめることは、キリストの神性を指し示すことにほかならない。ヨハネ福音書は、キリストが受肉した御言(Logos)である、と説く。ヨハネ一・一や一・一四をその文脈とともに見れば、ヨハネ福音書がキリストの神性をはっきりと教えていることがわかる。
さらに、ほかの言い回し(たとえばフィリピ二・六)もあるが、キリストが「神の子」であるという表現には特に注意しなければならない。新約聖書全体には百回も出るし、教会でも最も頻繁に使用されるからである。キリストは神の御子である。これはキリスト教の核心を表しており、キリスト教が固く保持する表現である。そこで「神」は、父なる神を指す。だから、新約聖書では(ごく少ない例外を除けば)、キリストは神である、とは言わない。後に、また現代にも見られるように、キリストが真の人間であり、真の神である、という表現は見られるが、そこでは、「神」を「神性」と解すべきである。ここに言う「神性」なる「神」は、キリストが父なる神の御子である、という以外の意味はないのである。「御子」というのは、父子の比喩をもって、キリストが本質的に神より出ずることを表したものである。つまり、キリストの神性を教えたものなのである。
キリスト教の歴史において、特に四世紀に、キリストの神性という問題が議論の的になった。それは、キリストの神性そのものが論じられたのか、それとも、神性を表す表現をめぐって議論をたたかわせたのか、ともかく、四五一年にカルケドン公会議は次のことを決めた。それは、すなわち、キリストは唯一のペルソナ(persona)であり、また、神性と人性という二つの本性(nature)を兼ね具えている、ということである。この決定は、神学におけるキリスト論の基礎になった。公会議の表現は、われわれにとっては、抽象的すぎるかもしれないが、キリストが完全に人間でありながら神性にあずかっていることは、疑いなく公会議の意図であり、また、キリスト教の基礎である。だから、公会議の表現にこだわらないで、同じことを別のことばで表現することは、いっこうにかまわない。たとえば、キリストは神と人間との接点であるとも言える。幾何学で言うように、接点は両領域のものである、とつけ加えればいい。
どういうふうに一人の人間であるイエスが同時に神性を有するかは、信仰は説明しない。神学者は、そこに矛盾はない、と教えるが、それだけにとどまる。キリストの神性を一つの「奥義」と名づける。この奥義を肯定しなければ、イエスの生涯も、キリスト教の存在も説明できないであろう。しかし、それができたところで、それは依然として奥義の証明にはならない。キリストの神性を信じるか、信じないか、の二者択一である。キリストの神性を認めることは、すなわち、キリストを信じることである。イエスを単なる人間であったと考える人は、クリスチャンではない。しかし、イエスを、神の子だと言わず、すぐれた人、超人間だとする人を、信者と認めるべきかどうかは明瞭でない。
キリストはどういう方か、という問いに、キリストの神性という一言で答えてきた。また、「主」とか「神の子」とかいう表現があることを指摘した。しかし、どういう表現を使っても、キリストのことを言い尽くすわけにはいかない。
キリストは一つの概念ではないからである。キリストは生きている「汝」であるから、どういうカテゴリーをも超えるのである。絶対者の前で、われわれのことばは貧しすぎる。
しかし、こういう疑問は起こりうる。キリストを「主」と呼んだ最初のクリスチャンと、「御言」という学者と、「神さま」と祈るいなかのお婆さんとは、はたして同じ信仰をもっているのであろうか、という疑問である。人によって表現は違うし、その表現の表す概念も違うだろう。各々違ったキリストを信じているのではないかと。なるほど、そう考えれば、主観的には、信仰が違うことになるかもしれない。しかし、信仰の対象はキリスト自身である。そのキリストは、だれにとっても同じキリストである。たとえて言えば、ある母が三人の子をもっているとしよう。それぞれの子どもの年齢や性格によって、各人の見る母はそれぞれ違ったイメージになるが、間違いなく同じ母である。信者によって、キリストのイメージは多少違うが、すべての信者の生きている相手は、唯一のキリストなのである。
Gネラン. キリスト教通信講座Ⅶ