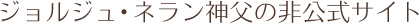「生きておられる」
西暦三〇年四月七日(金)午後三時ごろ、イエスは息を引き取った。
ところが、二日後の日曜日、イエスが復活して、生きているという噂が伝わり始めた。初め、それを信じた人は少なかった。十二使徒と他の弟子ぐらいだった。使徒言行録は百二十人という数字を挙げる。たびたび数字を水増ししている聖書の著者の傾向を考えると、百二十人以上だったとは思われない。とりあえずスタートは百二十一人だったとしよう。現在、世界人口の三分の一――統計によれば二八%――の人はキリストが生きていると信じているのである。
キリストは生きている。それはイエスの生前の姿に戻ったという意味ではない。イエスは死んで後、神のところへ移って神と共に生きているという意味なのである。だから、生きているキリストは時間と空間という次元に置かれていない。生きているが、それは目に見えない形である。
キリストは、このように永遠に普遍的に生きているからこそ、いつの時代にも、どんな所にも近くにいて、人に呼びかけることができるということになる。
イエスの死は史実である。が、イエスが死んでから永遠の命に移ったという復活は史実なのか。史実とは三次元に起こる歴史の出来事だとすれば、イエスの復活は史実とは言えない。キリストの復活はむしろ歴史からの脱出だと言える。
しかし、史実というものは証人の証言によって成り立つとも言える。その観点からみて、キリストが生きていると証言する人は極めて多い。しかもその中には、証言をするために命を犠牲にした人、すなわち殉教者は無数である。日本だけでも一万人もいるのである。パスカルの言うように「証人がそのために死を辞さない断言を私は信じようと思う」と。
生きているキリストは目に見えないが、その存在は教会と福音書というしるしを通して示されている。教会は信者の集まりであるだけでなく、キリストを内在する場である「二人または三人がわたしの名によって集まるところには、わたしもその中にいる」(マタイ一八・二〇)というキリストのことばは教会において実現する。福音書は地上のイエスの言動を伝えるばかりではなく、その読者に語るキリストの声でもある。「わたしは世の終わりまで、いつもあなたがたと共にいる」(マタイ二八・二〇)とキリストは言ったのである。
しるしがあっても、キリストはその姿が目に見えないので、生きているとは信じがたいと疑う人もいるかもしれない。信じがたいかどうかはさておいて、キリストが生きていることは信仰の対象であり、確実に証明されるものではない。換言すれば、キリストは人間の自由を尊敬して、自由を決断である信仰へ誘うという段階にとどまっていると言える。しるしを見抜く者は幸いである。
ところで、しるしというものは超越的なリアリティーヘ通じる唯一の道である。たとえばベートーヴェンの第五を聞くとする。その時、その曲の美に感動する。が、その美しさはどこにあるか、楽器の作る音の中にあると言っても、物質的現象である音そのものではない。やはり、超越的なものである美は音というしるしを通して伝えられる。キリストの超越的な存在もしるしを通してのみ把握できるのである。
もう一つ音楽のたとえ。キリストが生きているということは、ちょうど、モーツァルトが生きているというのと同じではないか、と考える人もいる。すなわち、モーツァルトがその作品によって今もなお生きていると同様、キリストもその福音によって今も生きているという見方である。
しかし、その比較は間違っている。私たちはモーツァルト自身に向かって祈りはしない。キリストは祈りの対象なのである。
Gネラン(1994). 季刊エポぺ 34号