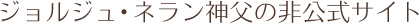あえて今、キリストの復活を
「キリストの復活」ということばを聞くだけで疑いを抱く人がいる。それには埋由がある。もちろん、キリストが復活したというのは、キリストがその生前の生活に戻ったという意味ではない。そうした誤解を解いても、なお疑問は残る。
キリストの復活は二千年も前に起こったことだから、歴史の出来事の一つと言えるかどうか疑わしい。目撃者はいなかったし、復活それ自体がこの世の現象でもなかった。キリストの復活は、キリストが神のもとに行くという意味なのだから。かりに、復活が史実だとしても、それは遥か昔に過ぎ去ったことではなかったか。
では、キリストの復活を宣言するのは、西暦三〇年の春、十字架上で死んだイエスのメッセージを宣べ伝えるだけだろうか。
たとえば、いま、モーツァルトの曲を聞くことができるので、モーツァルトが生きていると言える。同じように、残されたメッセージがあるからイエスは生きている、と言えるのか。そうではない。キリストは目に見えない形ではあるが、本当に生きている。生きているキリストに向かって信者は話したり、祈ったりするのである。
キリストが復活しなかったならば、キリスト教はナンセンスになる。それはパウロ自身の断言であり、現代の信者の立場でもある。そもそもキリストがキリスト教の教祖であることは間違いない。ところで、生前のイエスは教団を建設するための憲章や指令などを発しなかった。だから地上のイエスの言行と初代教会の信仰との間にずれがある。両者をつなぐもの、そして教会の基礎を築くのは、キリストの復活にほかならない。
キリスト教を成立させるのはキリストの教えだと考えられる。そしてその教えは「隣人を愛せよ」という教訓でまとめられる。ところが、愛はキリスト教固有のものではなく、他の宗教でも出てくる。キリスト教固有のものは、むしろ「わたしに従いなさい」というイエスの命令である。従うべき「わたし」は抽象的な理念ではなく、イエス自身なのだ。キリスト教の核心は生きているキリストである。そうして信者というのは、生きているキリストに属する者である。生きているキリストは、十字架で死んだキリスト以外のだれでもない。
復活を抜きにしてイエスの姿を描き出そうとする歴史家もいる。結果はさまざまだ。ある人によれば、イエスは政治に身を投じた反体制運動のリーダーであった。他の人はまた、博愛を説いた柔弱な夢想家であったと言う。こうしたイエス像は、キリスト教の核心であるキリストと縁のない空想である。
キリストが生きていると信じるのはキリストが復活したことを前提とする。キリスト教に関して興味をもつ人は、復活への信仰の要点とその範囲を、当然調べる。さらに、信仰の根拠である当時の証言を吟味し、検討しなければならない。
結論を出そう。トマスのように「わたしの主、わたしの神よ」と叫べる人は幸いである。
Gネラン(1997). 季刊エポぺ 46号