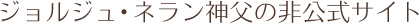信徒の病気は司祭依存症
なぜ、そのような状態になってしまったのだろうか。私が強調したいのは、宣教が小教区の教会がすることではなく、一人ひとりの信者自身が自分の住んでいる地域、働く職場などで取り組む課題であるということだ。晴佐久昌英師は宣教を「福音宣言」という言葉で表現している。教えることは難しいが、宣言なら誰でも可能である。
ところが残念なことに、日本では一人ひとりの信者の中で、自分の地域や職場で宣教活動を展開したことのある人はほとんど皆無に近い。司教をはじめとする日本の教会そのものが、そのような宣教活助の必要性を考えたこともなかったし、そうした提案が信者側から出されたこともない。
第二バチカン公会議のあと、日本では「信徒使徒職」という言葉が使われ、教会の中では司教、司祭だけでなく、信徒も宣教活助を担う役割、責任があるという発想のもとに全国規模の大会が開かれたこともあった。しかし、いつの間にか立ち消えになってしまったのである。その原因は、「宣教こそ信徒一般に課せられている課題であり、役割である」という信徒の使命が強調されてこなかったこともある。
しかし、私は日本の信者の大半が“司祭依存症”という病気にかかっているからだと思っている。信者の大半は日曜日に教会に行ってミサにあずかり、司祭の顔色をうかがって二言三言、話をして家に帰っていく。司祭の命令、指示がなければ何もしない。たとえ教会役員になっても、司祭の目の色をうかがい、司祭の機嫌を損なわないように行動して、それで事足れり、とする姿勢だ。まして司祭に関係なく自分一人で身近な人に宣教しようなどという発想を持ったり、考えたこともない信者が大半だと思う。それが私に言わせれば司祭依存症なのである。
Gネラン(2010). 福音宣教 10月号他