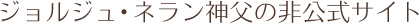【参考】宣教地の一時的なニーズに応えるための一時的な宣教会
'La Société des Auxi1iaires des Misssions'
カンペンハウド
普通の宣教会と異なって会員は宣教地の上着の司教のいる教区に限って遣わされるのです。また宣教地に会員がいても、会長はありません、その教区の司教以外に目上がないこの宣教会は会員に対する権利と義務すべてを司教に委ねます政治的な理由または健康の理由でヨーロッパに帰らなければならない場合に会員は再び宣教会のもとに戻ります。こういうような宣教会ができた理由を知るために、二十世紀のミッションの状況を知る必要があります。この会はアジアの十の国とアフリカの人つの国に会員を送つたが中国の宣教師ルップ神父の影響を受けて生まれたので、中国のミッションの状態を知る必要があります。
19世紀と20世紀初めの中国
19世紀の間に中国の帝国は弱くて、西洋の国に不平等条約を押し付けられました。その条約によって、中国は英国が阿片を自由に中国にもってくること、中国のいくつかの都会にヨーロッパの国々が租界を作ることも認められました。また西洋人が中国の法律に反した場合は租界に連れていかれそこで裁判を受けることになりました。同じ不平等条約でフランスは宣教師が中国のどこにでも居住し、また建物を造ることも中国に承知させました。キリスト教は阿片とともに中国に許されたことになります。
それに反発して義和団の反キリスト教運動は起こり、多くのミッションが害を受けました。その運動を滅ぼすために英国とフランスは戦い、再び中国が負けてしまいます。
しかし、そのころから中国の南に新しい中国が少しずつ生まれてきます。1912年に中華民国という政治運動が始まったが、日本との戦争と同時に国民党と共産党の内戦も始まります。ヨーロッパの戦争があって、1941年から外国の租界が少しずつなくなります。1949年共産党の勝利で、すべての租界はなくなります。
19世紀と20世紀の中国のミッション
20世紀の初めに不平等条約のおかげで、フランスは本国カトリック教会を迫害しているのに中国でカトリックミッションの保護国になったので、宣教師たちはいくつかの港の町だけでなく、中国のどこにでもミッションを開く可能性ができて、喜んでいました。しかし中国人のエリートは宣教師がヨーロッパの国の先駆者だと思うようになりました。
教会の中で、宣教師は中国人司祭に対して優越感をもっていて中国人司祭はいつまでも宣教師のお手伝いとして働くことが当然だと思われました。また、聖堂の中で宣教師を保護するフランスの国旗を掲げても問題がなかったが、中国の旗を掲げるならそれは政治行為だといわれて赦されませんでした。
しかし、レッブ神父と何人かの宣教師は中国人の司祭、神学性が愛国心を持つことが当然だと主張していて、また中国人が早いうちに司教にならないといけないと主張し続けていたので、中国人司祭と神学生をフランスの敵にしてしまうと言われて多くの宣教師から反対されました。ついにレップは言葉が通じない南の教区に追放されました。
ヨーロッパヘ中国人留学生の波
1919年と1921年の間、1500人以上の中国人留学生がフランスに来るようになりました。多くの学生が生活するために働かなければなりませんでした。周恩来と郡小平もその中の学生でした。ここで新しい中国は生まれつつありました。しかし彼らはフランスの反キリスト教の人たちの影響を大いに受けていました。
ローマから中国のミッションの問題を調査するためにバチカンから遣わされたパリー外国宣教会のデ・ゲブリアン司教は中国の教会の将来が今フランスにいる留学生の思想に大きく影響されるに違いないと痛感していました。中国人の司教の必要があることをレッブ神父と同じように望んでいたが、もう少し時間がかかると思っていました。彼はレッブ神父と宣教会の司教たちの問題を解決するためにフランスの中国人留学生のために働くことをレッブ神父に勧めました。レッブ神父はそれを承知しました。ローマにミッションの情報を伝えることもできるのではないかと思っていました。ベルギーのメルシエ枢機卿の紹介で、福音宣教所のバン・ロソム枢機卿に会うことができたし、その枢機卿の紹介でピオ畑世にも会うことができました。
ヨーロッパに戻ったレッブ神父はカトリック学校また寄宿学校とカトリック家庭がこの留学生を受け入れるように運動を始めました。そのおかげで相当の学生は洗礼を受けました。またカトリックになった学生のためにカトリック・アクションをつくりました。
それである時ベルギーに来て、ヴェルヴィエ市のある教会の助任司祭の家に一人の中国人の学生が住むようになりました。その助任司祭の名前はボランでした。この神父が指導していた若者のグループはレッブ神父のファンになって、ベルギーでレップ神父の秘書のようなものになりました。
宣教地に対するバチカンの動き
以上にも述べたように、1919年にパリー外国宣教会の広東の司教デ・ゲブリアンは福音宣教省に使徒的使命を受けて中国の北のミッションの状態を報告するために遣わされました。彼の調査がまだ終わっていないうちに、ベネヂクトXV世は「Maximm 11lud」の回勅を出しますGこの回勅はミッションについての新しい憲章のようなものです。先ず宣教会、修道会に委ねられた地域は会の固有のものではない、働き手が足りなければ、他の宣教会を呼ぶべきである、また土着の司祭が教会の責任を担うように早く養成すべきであるが。何世紀前から始めたミッションでもまだ司教になれる司祭が育てられていないことは残念であると嘆く、そして宣教師は自分の国のために働くために遣わされているのではなく、キリストの国を広めるために遣わされたことをいつも心掛ける必要があると注意しています。これは全くレッブ神父が望んでいたことです。
1922年に福音宣教省はコスタンティニ大司教を使徒的代表者として中国に送ります。この代表者はミッションについての権威を持っています。これはフランスのミッションの保護を弱める手段でした。コスタンティニ司教は中国人司祭に任される地区(使徒座知牧区)を準備しました。
1926年の初めにピオⅪ世は「Rerum Ecclesiae」の回勅を出します。その回勅はベネヂクトXV世の回勅をもっと厳しく新たにします。
同じ1926年にピオ測世はローマで最初の六人の中国人司祭に司教叙階を与えます。新しい司教たちに委ねられた地域には大きな都会はなかった。司教の任命によって使徒座知牧区は使徒座代理区になりましたが、そこに外国人の宣教師は残らなかった。その司教叙階が25年遅れたなら、中国ではカトリック教会に司教がいなくなって教会はどうなったでしょうか。その時からミッションの目的は「人の魂を救う」という言い方から「教会を植える」という言い方になりました。
1951年にピオⅫ世は「Evangelii Praecones」の回勅の中で、1959年にヨハネXXIII世「Princeps Pastorum」の回勅の中でまた同じように土着の司教と司祭たちの大切さ、また宣教師は自分の国のために働かないように再び注意なさいました。ピオXII世は最初の司教の叙階からもう25年ぐらいたっていたが、教区がその国の司教に任されるときに、そこに働いていた宣教師はその教区に残るようにお願いする必要がありました
宣教地についての教皇の回勅が36年間の内に四つあったことは教皇たちにとって土着の司教の必要性はどんなに重要であったかがわかります。
日本では
中国の司教叙階の一年後に、長崎教区は最初の日本人司教に委ねられたが、八年後に、日本の中心と言える東京にある大司教区に土井大司教が任命されます。戦争中の政治を考慮して、1940年と1941年の間に、すべての外国人の司教、使途座代理地区長は辞任しています。すべての外国人の宣教師は邦人司教の下で働くことになります。
しかし、宣教会、修道会の協力をスムーズにいただくために部分教会(教区、使途座代理区、使途座知牧区。これから教区の言葉だけを使うことにする)のある地域を宣教会、修道会に委ねることになりました。教区と宣教会の間に大抵25年の契約が結ばれて、その地区の中で宣教会、修道会には宣教を計画し、会計も任されていました。どこで新しい教会を立てるか、どういう女子修道会を呼ぶか、どういう宣教運動を起こすか、また司祭をどこに任命するかなどについて宣教会のイニシアチブは先にあって、教区長は承認するぐらいでした。司教は殆ど堅信と聖堂の祝別のためにだけにその地区に行ったぐらいと言えたかもしれません。しかし教区でのこういう地区の地区長の会議が多くなって、だんだん教区全体に対する司教の指導は強くなりました。そしてこのような契約は更新されませんでした。宣教会の地区はなくなって、宣教会の司祭はその国の司祭と共に働くことになりました。教区の会計は一本化になりました。
Société des Auxiliaires des Missionsの誕生
さて、もう一度中国人の司教叙階の1926年に戻りましょう。中国のリシエン県の新しい司教スエンはレッブ神父を連れて中国に帰ります。レッブ神父は宣教会の会長から許可を受けたが、使徒座代理区から出てはいけないという厳しい命令がついていました。
レッブ神父が中国へ帰ってから、ベルギーのヴェルヴィエ市のボラン神父は自分の司教の理解を得て、カトリック大学のあるルーバン市の中国人の学生寮に住むようになりました。彼の周りにいる何人かの司祭と神学生は中国人の司教の元で働きたいと望んでいました。これは珍しかったです、というのは中国人の司祭がある地域の司教になると、そこで働いていた宣教師が自分の宣教会・修道会の司教のいるところで働くために出ていくことになっていました。中国の何人かの司教は、レッブ神父の推薦によつて彼らを司祭も神学生も自分の教区への入籍を承諾してくださいました。中国の教区への入籍ができた神学生はヨーロッパの神学校に受け入れられました。
福音宣教省はヨーロッパの司祭が中国人司教の教区で働くことを励ましながらも、会を作るように望んでいました。病気のために、または働く国がビザを更新できない場合、ヨーロッパに戻った司祭を受け入れる団体がなくてはならないと主張していました。
しかし、教区司祭としてどうしても働きたい者は宣教会の会員になることを望みませんでした。そこで、新しい会が創られたが、会は司祭を宣教地の教区に遣わされるとき、会のすべての権利と義務をその教区の司教に授けます。ヨーロッパに帰る必要のある場合、司教は会にその権利と義務を返します。この宣教会は宣教師を養成し、アジアとアフリカに派遣し、また戻った人のケーアをすることが認められました。この会はあくまでも土着の教会を手伝うためだけにできているので名前の中に'auxiliaires'すなわち'補助者`という言葉があります。その国の司教の教区の司祭団の一人として働くことになりました。 `Société des Auxiliaires des Missions'という名前はミッションの補助者の会と訳せるでしょう。西洋人がもう上に立つ時代ではなくなって、お手伝いするために遣わされます。この会はラテン語の二つの言葉の大文字を使ってSAMと呼ばれるようになりました。これからSAMという名前でこの宣教会を呼びます。
1930年に最初の会員が中国の司教のもとで働くために中国に行きますがインド、ベトナムなどの教区にも遣わされます。土着の司祭は教区のレベルで働く要請をされていなかったし、宣教師もいなくなったので、教区に入ってくるSAMの司祭は小教区で働くほかにも神学校で教えたり、司教の秘書になったり、教区の財務の基礎を作ったりするなどのことを頼まれました。
1952年ごろ、アジアの十の国、アフリカの入つの国で働いていました。各国のいくつかの教区の中で働いていました。会員は七つの国から来ていた。SAMの歴史の絶頂には100人のメンバーがいました。
25歳ぐらいの青年を一人でその国の言葉も知らないで、その国で誰も知らないなかに遣わすのは冒険だと言われて、いろいろのところからSAMは反対を受けていました。そのころ、土着の司教に教区が委ねられると、大抵の宣教師がその教区から出ていくのに、たった一人でその教区に働きに行かせることはやはり理解は難しかったでしょう。
日,本こには1951年に最初横浜教区に一人(カンペンと呼ばれたカンペンハウド師)、続いて東京教区二人(デフレーヌ師とネーラン師)、仙台教区一人(ムラカベと呼ばれたデグクテエネール師)、新潟教区一人(アンリと呼ばれるホイセゴムス師)、京都教区にも一人いたがこの人はうまくいかず国に帰りました。
SAMの使命の終わり
年がたつにつれて変わったことは宣教師たちは問題なく土着の司教の下で働くようになりました。それは宣教地のニーズがある意味でいろいろの方法で果たされたことだと言えましょう。
もう一つの理由もあります。それは1957年にピオⅢ世の「Fidei Dontm」の回勅の影響がありました。ピオⅦ世はヨーロッパと米国の司教たちに全世界の宣教の責任を一緒に持ってもらおうと思って、彼らに自分の教区の司祭をアフリカの教区に何年間か貸してくれるようにと願いました。アフリカでは言葉の問題はあまりなかったので、司教たちは良くその願いに答えてくれました。1961年にヨハネXXIII世はその運動を南米の教会に広げられました。
宣教地のニーズがいろいろの方法でよく果たされていると判断して、1977年にSAMの総会で、SAMが果たすべき使命は果たされ、その精神が広まったと判断して、SAMの使命が終わったと考え、新しい会員をもう入れない決定をしました。
10年、15年ぐらいの間でも教区司祭が働きにくることは二つの教区を結ぶ大切なコムニオを示すことになります。大変喜ばしいことです。しかし、新しい教会に自分を一生涯ささげて、神から与えられた国を自分の国とし、そこで司教のもとに、司祭団の一人として働くことはまた別のあかしです。生まれ変わるほどの兄弟愛のあかしです。
ヨーロッパの教区では司祭が十分にいないがもっと司祭を必要とするほかの教区に司祭を送ることは教会同士の兄弟的な交わりの素晴らしい証です。神に感謝することです。しかし50年前に考えられなかったもう一つの素晴らしいことについて神に感謝すべきです。それはアジアとアフリカの教区から司祭が足りなくなったヨーロッパに司祭を貸してくれることです。
SAMが応えようとした教会のニーズはいろいろの方法で果たされています。神に感謝。