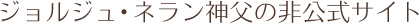『ろごす』
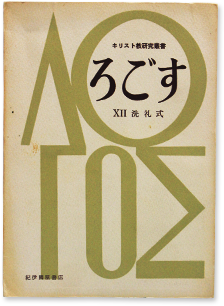
< 目 次 >
- I 「復活」
- 1.復活のケリグマ(J.Schmi枕一広瀬京一郎)
- 2.聖書における「栄光」の意義(J.Duplacy-渡辺義愛)
- 3. エマオの聖餐(J.Dupont-山崎庸一郎)
- 4.復活の意義について(j.Guitton,広瀬京一郎)
- 5.パウロのキリスト観(F.X.DuITwwe1一三雲夏生)
- 6・パウロによるキリストの復活とキリスト教徒の復活(LCeIfaux-稲垣留女)
- 7.ヨハネにおける「生命」-----信仰者の生命たるキリスト----(j.Dupont-武者小路公秀)
- 8.復活についてのアウグスチヌスの講話(長江意訳)
- 9.われらの内なるキリスト グワルディーこの『新約のキリスト像』より一(神山四郎訳)
- 10.復活せるキリストの現存 一フラソソワ・モーリャックー(布川公子訳)
- II「キリストの体」
- 1.パウロにおけるキリストの体たる教会(A・Chavasse三雲夏生)
- 2.パウロの「共」を用いた熟語(G・ネラン)
- 3.キリストとの合体としての洗礼(G・ネラン-----渡辺義愛)
- 4.体・頭・充溢(P・Bermt------三雲夏生)
- 5.アウグスチヌスの立場(井上洋治)
- 6.トマス・アクイナスの教え(沢田和夫)
- 7.葡萄の樹の誓え(A・George -----内山修)
- 8.ミステイクー言葉の歴史について(M.deCerteau-------武者小路公秀)
- 9.神秘体についての回勅に関して(G.ネラン------井上洋治)
- 10.この世におられるキリスト(ニューマソ)(巽豊彦訳)
- 11.ワルシャワ大司教の声
- III「エレミヤ」
- 1.序章
- 2.エレミヤの生涯(A.Gelin渡辺義愛)
- (1)エレミヤの生涯
- (2)初期の説教
- (3)ヨシャとエレミヤ
- (4)エソフトの旗のもとに
- (5)バビロン-----怒りの鞭
- (6)エレミヤの『述懐』
- (7)国粋王義との抗争
- (8)エレサレムの陥落
- (9)メシア期待の立場
- (10)終焉
- (11)エレミヤの影響
- 3.エレミヤの新約的意義(A.duCerteau-------武者小路公秀)
- IV「結婚・独身」
- 1.聖書の教え(G・ネラン-----武者小路公秀)
- 2.教会における独身制度の起り(G・ネラン-----岩瀬孝)
- 3.聖なる童貞について ------聖アウグスチヌスの論文より------(長江恵訳)
- 4.童貞の歌 一ローマ司教典礼書より一(長江恵訳)
- 5.愛の実現としての結婚(広瀬京一郎)
- 6.独身の精神(G・ネラン------高橋勝)
- 7.司祭の独身
- 8.戦死したある青年将校の手紙より
- 9.「私は独身を後悔しない」(Y.Bouge一中川富美子訳)
- 10.キリストに倣う独身生活の犠牲(M.Thunan-安井源治抄訳)
- 11.「探き淵より』(J.Bemhart-粕谷甲)
- 12..神学と在俗信者E(ゲスマソ------高橋憲ー)
- 第V輯「祈り」
- 1.祈祷文(白石明・高橋勝)
- 2.典礼について(G・ネラン----広瀬京一郎)
- 3.祈りの底にあるもの(奥村一郎)
- 4.キリストの祈り(G・ネラン----三雲夏生)
- 5.使徒職と祈り(L.Lochet------武者小路公秀抄訳)
- 6.無言
- 7.家庭の祈りの一例(安井源治訳)
- 8.聖書における主な祈り文
- VI「聖書の読み方」
- 第一部 聖書概説(白石明・中島文夫)
- 1.序論
- 2.パレスチナ定着
- 3.モーセ五書
- 4.王朝時代
- 5.捕囚期以前の預言者
- 6.捕囚と帰茂
- 7.知恵文学
- 8.黙示文学
- 9.新約聖書
- 第二部 文学的研究(G・ネラン-----武者小路公秀)
- 1.文学的ジャンル
- 2.エデンの能
- 3.架空座談会 ヨブ記
- 4.各種の伝承の解義
- 5.主題の拡大
- 6.再解釈
- 第三部 「聖書」は「神の言葉」である(佐藤千敬)
- 1.「書物」としての聖書
- 2.『聖典としての聖書
- 3.聖書の「原典」・「写本」・「翻訳」
- 4.聖書の『多様性』と「統一性」
- 5.「聖書」は真に「神の言葉」である(キエルケゴールの日記より)
- 第一部 聖書概説(白石明・中島文夫)
- VII「神の軌跡」
- 1.存在における神の軌跡一創造の諸問題に焦点を求めて一(小松茂)
- 2.至福なる神の現存(三雲夏生)
- 3.美しい神の足跡(野村良雄)
- 4.芸術に見る超越と自由(AAyfe一白石明)
- 5.歴史の中なるキリスト・イエズス---一つの歴史神学的考察一(沢田昭夫)
- 6.神と技術
- 7.ティヤール・ド.シャルダンのキリスト教観
- 8.ロマン・ロランにおける神の諸相(Pリーチ-----長戸路信行)
- VIII「経済社会と人間」
- 第一部 教会の社会教説(澤田昭夫)
- 1.教会の社会教説一源泉・性格・権威)
- 2.教会の社会数説と社会主義・共産主義)
- 3.ヨハネス23世の回状
- 4.人間と社会
- 第二部 経済社会の基本構造(岡田純一)
- 序論
- 1.欲求
- 2.所有
- 3.労働
- 4.資本
- 5.交換・価格・市場
- 6.企業
- 7.国民経済と国際経済
- 8.経済と国家 結語
- 第一部 教会の社会教説(澤田昭夫)
- IX「人となった神」
- 1.カルケドソの教義(N.deRangy------広源京一郎)
- 2.新約聖書の通しるべ(G・ネラン----渡辺義愛)
- 3.共観福音書にあらわれたイエズスの奇跡(A・George--長戸路信行)
- 4.奇跡の神学的考察(長戸路信行)
- 5.人の子(G・ネラン---澤田和夫)
- 6.共観福音書における「父」と「子」(A・Geore-------高橋勝)
- 7.第四福音書におけるイエズスと「父」(J・Glblet------久米あつみ)
- 8.神の僕なるキリストへの項歌(ピリヒ書2,6-11)(広瀬京一郎)
- 9.御言は肉となった(佐藤千秋)
- 10.キリストの自意識(白石明)
- 11.レオのトムスコンスタンチノポリスの司教フラピアノスヘの書簡一(熊谷賢二訳)
- X「神の国」
R.Schnackenburg--------田川建三- 第一部 旧約と後期ユダヤ教における神の王支配
- 1.旧約聖書
- 2.後期ユダヤ教
- 第二部 イェススの宣教における神の王支配
- 1.イエスによって宣教された神支配(一般的性格)
- 2.終末観的神支配がイエスの活動の中に実在している
- 3.完全な神支配の到来
- 4.神支配と敦の共同体
- 第三部 初期キリスト教の宣教における神支配
- 1.復活後の教会における神支配の解釈
- 2.ハウロにおける神支配
- 3.新約後期の文書における神の国
- 第一部 旧約と後期ユダヤ教における神の王支配
- XI「祭司と司祭」
- 1.旧約時代の祭司(R.deVaux-渡辺義愛
- 2.へブル人への手紙における大祭司キリスト(G・ネラン----久米あつみ)
- 3.祭司たる信者(N・deRangy-長戸路信行)
- 4.新約聖書における教会の役務(白石明・中島文夫)
- 5.ヒッホリトの「伝承」より司教叙階式(黒岩一)
- 6.トレント公会議における「叙階の秘跡」(佐藤千敬)
- 7.司祭職(G・ネラン----広瀬京一郎)
- 8.司教叙階式の日の説教(アウクスチヌス)(澤田和夫訳)
- XII「洗礼式」
- 1.洗礼式の史的解明(粕谷甲一)
- 2.洗礼式史の文献について(白石明)
- 3.現行洗礼式詳解(白石明)
- 4.神学的考察(G・ネラン----広瀬京一郎)
- 5.エルサレムのキリロスのカテケシス(G・ネラン・川添利明訳註)
- XIII「宣教論」
- 1.新事態(G・ネラン)
- 2.法律神学試論(澤田和夫)
- 3.労働法の発展の歴史(澤田和夫)
- 4.日本人と結婚(遠藤周作)
- 5.ヨーロッパ共同体のヴィジョンと現実 一社会政策と計画上をめくって一(岡田純一・三保宏)
- 6.神への欲求(G・ネラン---広瀬京一郎)
- 7.神のみわざの客観性(G・ネラン----広瀬京一郎)
- 8.方法論について(G・ネラン----三雲夏生)
< 参 考 >
『ネラン師遺稿集(資料集)』より
ネラン師は、長崎にいた時、論語を日本語で読んでいた。東京に赴任していた時に既に原稿は日本語で書かれていた。日本語の漢字は書き順が少々違うが、非常に難しい漢字を使用していた。恐らく、下記にあげるネラン師の著書は日本語で推敲して居たろう。
ネラン師は多くの著書を残した。その中で、代表的な著書は「ロゴス」である。何故かネラン師は「ろごす」と平仮名で表紙を造った。この本は、13巻ある。発売元は紀伊国屋書店、発行は昭和39年とあり大作である。
『ネラン神父の「日本語で推敲していた」について』
(EISEI)
「ネラン師の著書は日本語で推敲していた」とあるが、本当にそうであろうか?
『ろごす』で、筆者「G・ネラン----渡辺義愛」とあるのは、ネラン神父がフランス語で書いて、渡辺氏が翻訳したということである。ただし、「白石明」はネラン神父のペンネームだから、その文章は日本語で自身が書かれたのだろう。当時は、自覚して、使い分けていたと思われる。
確かに、晩年は『エポペ通信』等、多くの文章を日本語で書いている。
ただ、『キリスト論』や『キリストの復活』等の神学論文は、日本語で書かれているが、そのまま「日本語で推敲」して書いたのかは、今となっては<謎>である。
その可能性は高いといえるが。
なぜ、そういうのかというと、アンリ神父は講演原稿も説教も、一旦フランス語で書いて、ご自身で日本語に翻訳する。ネラン神父『未公開の日記』もフランス語で書かれていた。
日本語で文章は書けても、「日本語で推敲する」ということは、我々が想像するより遥かに困難なことだと、いわねばならない。