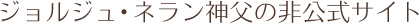『キリストの復活』
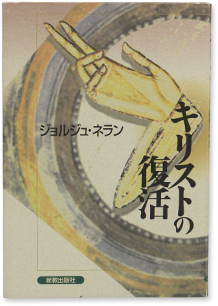
< 目 次 >
- 1. オリエンティーション
- 2. 信仰の表現
- 3. 最初の証言
- 4. 日曜日の早朝
- マルコ伝
- マタイ伝
- ルカ伝
- ヨハネ伝
- 5. 使徒団の前に現れた
- マタイ伝
- ルカ伝
- ヨハネ伝
- 6. 弟子たちの個々人の前に現れた
- 婦人たちの前にあらわれた(マタイ伝)
- エマオで二人の弟子の前に現れた(ルカ伝)
- マグラダのマリアの前に現れた(ヨハネ伝)
- 七人の弟子たちの前に現れた(ヨハネ伝21章)
- 7. パウロに現れた
- ルカの記述
- パウロの話
- 8. 出来事としての復活
- イエスの時代の死者復活に対する希望
- 三日目に
- 空になった墓
- 神になさったわざ
- 史実といえるか
- 信仰の対象
- 9. 出現
- 信者の信びょう性
- 信仰に観点から見て
- 10. 死を超克する
- 11. 生きるキリストの軌跡
- パウロによるキリストの合体
- ルカによる救い
- ヨハネによる命の賦与
- あとがき
- 司祭・宣教師・キリスト信者
(ジョルジュ・ネラン神父葬儀ミサ説教(カトリック東京大司教区補佐司教 幸田和生)
[この内容は、このサイトの『講演録』に掲載されています。]
- 司祭・宣教師・キリスト信者
1.オリエンテーション
キリストが復活したというのは、イエスが生前の生活に戻ったという意味ではない。イエスがこの世を去って神の世界に入ったということである。換言すれば、復活したキリストは神のもとにいて、永遠に生きているが、それは人間の目に見えない形での存在である。
復活の光景を目撃した人はだれもいないし、聖書のどこにもそれは描かれていない。復活のメッセージによってのみ復活を信じるのである。したがって、復活の出来事と復活のメッセージとをはっきりと区別しなければならない。復活のメッセージ------キリストが復活したという宣言------は、弟子たちの前にイエスが現われた出来事に由来する。キリストの出現を体験した弟子の証言を聖書は伝えるのである。
ところで、キリストが現れたのは、限られた人の前に、限られた期間に、限られた回数である。それ以外の人々はだれも復活したキリストを見てはいない。これはキリストの復活に物的証拠がないことを意味する。キリストの復活はあくまでも信仰の対象である。
「見ないのに信じる人は幸いである」(ヨハネ20・29)というヨハネ福音書の言葉は、まさにわたしたちのことを言いあてている。
死んだ人が今もなお生きているとは実に信じがたい話だ。にもかかわらず、キリストの復活はキリスト教の信仰である。否、キリスト教の土台である。パウロのいうように、「キリストが復活していないのなら、わたしたちの教えはナンセンスである」(一コリント15・14)
本書では、キリストの復活を信じるのはどういうことか、またどういう根拠によって信じるかを述べようと思う。まず、聖書のデータをできるだけ詳しく検討する。次に、復活の意味、墓のしるし、出現の現実性などを考察する。そして、最後にわたしたちにとっての復活の意義を指し示すつもりである。
あとがき
一九七九年に上梓した『キリスト論』の序論で、私はキリストの復活という問題を割愛すると書いた。大変遅くなったが、本書はその部分を補おうとするものである。キリストの復活について日本語で書かれた書物は極めて少ない。あるとすればほとんど翻訳だから、それらは西洋人の見方を反映しており、必ずしも日本人の関心に応えるものではない。このような状況のもとでの本書の出版は意味のないものではないと信じている。
日本語で出版された本には次のようなものがある。
*ウルリッヒ・ヴィルケンス『フッカツ』、新教出版社、一九七一年
*X・レオンⅡデュフール『イエスの復活とその福音』、新教出版社、一九七四年
*W・マルクセン他『イエスの復活の意味』、新教出版社、一九七四年
*F・X・デュルウェル『キリストの復活』、南窓社、一九七五年
*山内真『復活』、日本基督教団出版局、一九七九年
*藤井孝夫『キリストの復活事件と教会』、新教出版社、一九八七年
*ヴァルター・キュネット『復活の神学』、新教出版社、一九九三年
*レイモンド.E・ブラウン『キリストの復活』、女子パウロ会、一九九七年
以上の研究には豊富な参考文献が提示されている。
なお、私は、書物中での参考文献への指示や注釈は読者にとって煩わしいものと思うから、本書ではそれらはすべて省いた。
Resurrexit,E.Dhanis ed, Citta Vaticano,1974 という研究書は、一九二〇年から一九七三年まで出た復活に関する書物と記事のリストを掲載している。このリストは一四三三項目からなっている。一九七三年以降現在までさらに百項目以上が追加されたはずである。私はそのすべては読んでいないことを告白する。(重要なものは読んでいるつもりだが)
本書はキリストの復活について言えることを言い尽くしたものではない。他にもさまざまな問題点や見方がある。とはいえ、私の選んだ論点とその解釈が突飛なものでも恣意的なものでもないことは確信している。
本書は翻訳ではない。私が初めから日本語で書いたものである。ただし、日本語の文章表の面では、文教大学文学部遠藤藤枝教授からいろいろ教えを受けた。ここで厚くお礼を申し上げる。
なを、新教出版社がこの本を刊行してくれたことに深く感謝している。